

私もフルパワーで頑張ります!


前回の会議でピックアップした投資信託の商品に続いて、今回は投資信託についてさらに深く調べてまいりました。



今回の会議はより一層楽しめそうだ。
では早速調査報告をよろしく。

改めて投資信託の復習をしよう
インデックス型とアクティブ型

投資信託は、大きく分けてインデックス型とアクティブ型の2つです。
インデックス型は日経平均株価やTOPIXなどの指標と連動することを目指して運用する商品で、手数料が安く長期運用に向くと言われています。


長期運用で複利効果が生まれるということで、インデックス型をおすすめする本や雑誌も多いです。
対してアクティブ型は、あらかじめ定めた指標よりも高い収益率を獲得することを目指して運用されます。
投資信託全体の約8割以上なので、ほとんどの商品がこのアクティブ型です。
インデックス型よりもハイリスクハイリターンで、運用者であるファンドマネージャーの腕によって運用成績が変わります。


ただ、アクティブ型はインデックス型よりもハイリターンを狙えるというのに、実際には運用成績が悪いものが非常に多いんです。


でも、投資家としては手数料を余計に払ってプロに託しているわけですから、それで成績が悪かったら意味がありません。
だから、比較的安全に運用できて、アクティブ型よりも成績の良いインデックス型をすすめる専門家や雑誌が多いということです。


毎月積立型と毎月分配型

圧倒的に人気があるのは毎月積立型と毎月分配型の商品です。


まず毎月積立型の商品は、毎月決まった金額分コツコツ購入していくもので、まとまったお金がなくても、少額から始められるというメリットがあります。
基本的には長期運用が前提です。
利益分を再投資すれば、複利効果の恩恵を受けることもできます。


少額から始められるので、投資初心者や主婦の方、若い年代にとくに人気があります。

若いうちはお金がないし、投資信託を始めようにも選択肢は毎月積立型しかないとも言えるかな。

余裕資金はない、だけど時間は比較的ある、ということで長期運用の毎月分配型が人気なんだと思います。

では毎月分配型の説明をよろしく。

投資信託の収益の一部を投資家に還元するお金を分配金と言います。
一般的には決算時に支払われますが、毎回同じ金額ではありません。
まったく支払われない場合もあります。
また、元本の一部を投資家に返す特別分配金というのもあり、分配金が出ているからと言って、必ず利益が出ているわけではありません。

では、この商品が人気なのはなぜ?



【家来のMore detail room】分配金について説明いたします
実際にはあり得ませんが、分かりやすくするために、基準価額や元本は変わらないものとして説明します。
また家来調べでは、分配金が100円~300円という商品が目立ったので、毎月分配金は200円とさせていただきます。
まず、基準価額1万円(1万口)の毎月分配型の商品を、500万円分(500万口分)購入しました。
分配金は1万円(1万口)に対して200円ですから、1口当たり0.02円ということです。
なので、500万円(500万口)×0.02円=10万円。
つまり毎月10万円が分配されるということです。

毎月5万とか10万円が貰えるって、なんかお小遣いみたいだな。



毎月200円分配の商品を5万円購入した場合は毎月貰えるのは1,000円です。

家族でファミレスにも行けないよ。

驚きです。
今度ご一緒させてください。
というわけで、毎月分配型は、リタイア組や年金組の年配の方に人気があります。

とくに最近は年金も減ってきているし。


年金の話はこれから頑張りますとして話を戻すけど、すべての毎月分配型の商品が、運用資金を確保して、かつ毎月分配があるというわけではないんだよね?

分配金の説明でも触れましたが、分配金は変動することもあれば出ない時もあります。
また、特別分配金のように投資家から集めたお金の一部を還元している場合もあります。
ですので、運用資金をすべて守りつつ毎月の分配も貰えるというのは理想ですが、現実的にはそれほど多くありません。



【家来のMore detail room】毎月分配型商品について補足いたします
投資信託の基準価額は、資産総額(純資産額)を投資信託の口数で割ったものです。
資産総額には、運用によって得られた利益なども含まれています。
なので、分配金が出れば資産総額が減るので基準価額も下がることになります。
では、毎月分配型の商品「V」と「W」にそれぞれ500万円ずつ投資したとして説明しましょう。
どちらも分配金は毎月10万円です。なので、1年でトータル120万円貰えます。
ちなみに分かりやすいように手数料や税金などは、すべて省きます。
| 商品名 | 1年後の運用資金 | 分配金受取額 | 運用資金+分配金 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 「V」 | 400万円 | 120万円 | 520万円 | +20万円 |
| 「W」 | 300万円 | 120万円 | 420万円 | -80万円 |
どちらも分配金が支払われたことで基準価額が下がり、1年後には運用資金が減りました。
そのため商品「V」は、分配金を合わせるとトータル520万円となりプラス20万円。
商品「W」は分配金を合わせても420万円にしかなりませんから、トータル80万円のマイナスとなります。
どちらも毎月10万円の分配があるので同じようにお得に感じるかもしれません。
しかし実際にはトータルでマイナスになっているケースもありますし、たとえプラスでも毎月の分配金の割には、思ったよりも少なくなっているかもしれません。
なので、分配金の金額にだけ注目してはいけないということです。

運用資金が減る可能性を無視して、毎月いくらの分配金が貰えますということだけを強調するようなセールストークには、簡単に騙されていけないと。

それを信じて、みんなが買っているから安心だ、運用もうまくいっているんだと安易に飛びつくと、実は…ということがあるわけです。

住宅ローンを退職金で完済できる、けど年金だけでは不安だから手元にある程度お金は残したい。
おっ!毎月分配型投信なら、退職金も残せて毎月10万円の分配金は住宅ローンに充てられるぞ!これなら何とかなりそうだ!
みたいにならないようにってことだね。

ただ、もちろん運用成績が良いものもあるので、結局のところしっかり商品を見極めてくださいということになりますが…。

ところで、毎月積立型や毎月分配型が人気なわけだけど、毎月積立分配型ってあるの?

1万円に対して毎月分配金が200円の商品を、毎月500円ずつ積み立てていくとすると、1ヶ月後に分配金10円、2ヶ月後は20円、1年後は120円となり、この1年で貰える分配金の合計額は780円となります。

では次の質問、毎月分配型は償還日ってあるのかな?

償還日のない無期限の商品も少なくありません。


運用資金が減るということは運用にも影響が出てしまいます。
なので、多くの毎月分配型の商品は償還日が設定されているということです。
もし償還日よりも前に運用できなくなれば、無期限の商品も含めて繰上償還することとなります。


王国の財政を立て直すには、毎月分配型の商品は向かないと思います。

よし。王国では毎月分配型の投資信託は購入しないということで決定しよう!

ということで、以上が投資信託のおさらいでした。
インデックス型よりもアクティブ型の商品をおすすめする理由
篠田尚子(著)『本当にお金が増える投資信託は、この10本です。』


良い情報だといいけど…。

実は前回の戦略会議の後に、1冊の本を読んだんですよ。







新商品もどんどん発売されるわけだからそれは大変だね。
篠田さんみたいなファンドアナリストって国内に結構いるの?



なかでも篠田さんは、世界最大の投資信託評価機関のリッパーという会社でも調査や評価業務に携わっているので、世界の投資信託事情も詳しいということです。


それぐらい投資信託を知り尽くした篠田さんなので、銀行やファイナンシャルプランナーも知らないような、国内のある定説によって埋もれてしまった本当に優れた商品がある、と明言しています。


だから本を読むと、いかに世間に広まっている常識は間違いだらけだと分かりました。

年代別おすすめ商品は存在しない


今日の会議でも言ってたよね。

それだけでなく、若い世代はある程度リスクが取れるので海外の株式中心の商品をとか、60代を過ぎればリスクを避けるために国内の債券に投資する商品をといった内容も同じです。
本では、そんな年代別おすすめ商品は存在しないと断言しています。

断言する理由は何?



確かに長期投資によって、トータルプラスや最小限のマイナスで抑えられる商品が多いのかもしれませんが、リスクの大きな商品は、いつでも同様に損失を被る可能性があるわけです。



若ければ今後収入が増えていく可能性が高いから、リスクは多少負ってもその収入増でカバーできるかもしれない。
だから、年代別おすすめというのも間違っているとは思えないんだけどね。




60代にとって非常に良い商品なのに、30代ではおすすめできない、悪い商品だ!にはならないってことか。

本当に優れた良い投資信託の商品であれば、年代関係なくおすすめになるわけです。

分かりやすい説明だったよ。
人気(販売)ランキングの上位だからといって運用成績が良いとはかぎらない




毎月分配型の販売実績が良いと言ってたのはそういう理由か。
毎月お小遣いが貰えるというようなセールスポイントが沢山あるからみんな購入する、すると販売ランキングが上位になる、さらに商品をアピールできてみんなが安心して購入する…のサイクルね。


俺はこれまで販売ランキング上位の商品にハズレはないと思っていたから、購入前に聞いておいて良かった。
他の情報は?どんどん聞きたいよ。
投資信託に複利は存在しない


インデックス型は利益分を再投資して、長期運用すれば複利によってお金を増やせる…というのは違ったの?

なので、投資信託に複利は存在しません。


しかし投資信託の場合、元本は保証されてませんし、運用成績も変動するので、何年後にいくらになるというのは、あくまで期待値とか目安にすぎないということです。
ですから表現の仕方にもちょっとした違いがありまして…




ですから、預貯金のような『複利』という表現や表示はできません。
そこで、あくまでこのように運用すれば、複利のようにお金が増やせますということで『複利効果』という表示を使う場合が多いようです。
『複利』と『複利効果』は非常に似てますが、中身がまったく違います。




【家来のMore detail room】複利と運用成績が変動した場合の違いについて説明いたします
例えば年20%の運用を掲げる商品が募集されたので、100万円を購入したとします。
この商品は運用成績が年20%と魅力的なので、販売会社は「100万円購入すると複利効果で5年後には約250万円、10年後には約620万円に!」と大々的にアピールしやすくなります。
投資する側はその文言だけを見れば、複利でそれだけ増やせると思いますから、販売実績も伸びていくでしょう。
しかし、投資信託の運用成績は変動します。
| 運用成績 | 10年後 | 複利との差額 |
|---|---|---|
| 毎年20% (複利) |
約620万円 | |
| 1年間-20% | 約413万円 | 約207万円 |
| 2年間-20% | 約275万円 | 約345万円 |
| 5年間-20% | 約82万円 | 約538万円 |
| 5年間-5% | 約193万円 | 約427万円 |
| 5年間+5% | 約318万円 | 約302万円 |
|
||

例えば1年目だけ-20%と、8年目だけ-20%とか。
2年間とか5年間とか、例に挙げた他の運用成績についても同じです。

1年間マイナス20%になるだけで、207万円も減ってしまうんだね。
セールストークで複利効果の話を聞いたとしても、それだけのお金が必ず増えると勘違いしてはいけないな。

なので、投資信託における複利というのは机上の空論ですから、目安くらいに思っておきましょう。
上昇率(騰落率)が高くても良い商品とはかぎらない



その基準価額がある期間においてどれくらい変動したかを、上昇率や騰落率によって表します。
この上昇率や騰落率が高ければ商品のアピールポイントとなるので「ここ1年間で何%も値上がりした素晴らしい商品です!」のような表示も多いかと思います。

でも値上がりしているんだから、上昇率が高ければ高いほど良い商品なんじゃないの?

たとえば…

【家来のMore detail room】上昇率(騰落率)について説明いたします
運用開始から3年経った3つの商品があるとします。
それぞれの基準価額の変動を見てみましょう。
運用開始時は基準価額はすべて10,000円です。
| 商品名 | 運用1年後 | 運用2年後 | 運用3年後 (現在) |
|---|---|---|---|
| 「X」 | 7,500円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 「Y」 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 |
| 「Z」 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
商品「X」は、運用開始後2年目までは運用成績が悪く、その後持ち直して3年後には10,000円まで回復しました。
商品「Y」は、1年目の運用成績が良かったものの、徐々に基準価額を下げていきました。
商品「Z」は、平均的に右肩上がりの運用成績で、基準価額を上げていきました。
では、この3つの商品を上昇率(騰落率)で見てみましょう。
| 商品名 | 直近3年 | 直近2年 | 直近1年 |
|---|---|---|---|
| 「X」 | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
| 「Y」 | 30.0% | -13.3% | -7.1% |
| 「Z」 | 60.0% | 33.3% | 14.3% |
直近1年だけを見ると、「X」の上昇率は100%で、他の2つとは比較にならないほど上昇しています。
直近2年だけを見ても、「X」と「Z」は同じ上昇率です。
「Y」にいたっては、直近1年2年ともにマイナスです。
基準価額がある期間内値上がりしていれば、上昇率はプラスになります。
なので上昇率が高ければ高いほど良い商品だと思いがちです。
しかし、現在の基準価額を比較するとどうでしょうか。
「X」は10,000円、「Y」は13,000円、「Z」は16,000円です。
「X」は直近1年の上昇率が100%なので凄い商品と思ってしまいますが、実際は3年前と同じ10,000円まで回復したに過ぎません。
3年前に購入した人は、まったく得をしていないことになります。
「Z」は直近1年だけ見れば14.3%と、「X」に比べれば地味な値上がりに見えますが、実際は常に右肩上がりの良い商品です。
「Y」はマイナスが続いていますが、「X」よりも基準価額は3,000円高いです。
とはいえ「X」も直近1年と同様に運用がうまく可能性はあるので、この先他の2つよりも基準価額が上がるかもしれません。
結局、上昇率(騰落率)だけを見てしまうと、運用が常にうまくいっている「Z」のような、本当に良い商品を見極められないということです。

「X」のような商品が多ければ多いほど、本当に良い商品が序章率ランキングでは目立たなくなってしまうんだね。

しかも、「Z」の基準価額は右肩上がりなので運用担当者は優秀な可能性が高いです。
それなのに、たまたま直近の1年だけ運用がうまくいったかもしれない「X」のような商品があるために、本来優れた商品が隠れてしまいます。

まぐれの可能性があるということね。

この商品は、指標の株価が下がっていれば、基準価額も連動して上昇率がマイナスになりますから、マイナスだからと言って運用担当者が下手だというのは早計です。

勘違いしないように長い期間での上昇率や連動する指標の動きも見ていかないとな。
株とは違って基準価額が下がっても狙い目とはならない

投資信託では「基準価額が安い商品は逆に狙い目」とも言われることもありますが、正しい表現とはいえないそうです。


でも、投資信託は株とは違います。


株は売りと買いの需要と供給によって株価が決まります。
そのため、買いが増えれば株価も上昇していきます。
だから、低位株のように株価が安いと、購入費用が抑えられますし、その後買いが爆発的に増えれば5倍10倍と株価が上昇する場合もあるので狙い目となるわけです。


でも、基準価額は株のように買いが増えたからといって基準価額は上がっていきません。


【家来のMore detail room】なぜ基準価額が上がらないのか説明いたします
それは投資信託の値段の決め方、算出方法にあります。
基準価額=純資産総額÷総口数
純資産総額は、投資信託で運用している金融商品の、株の配当や債券の利息なども含めた資産の総額から、必要経費を差し引いたものです。
総口数は、商品を購入した人(投資家)が保有する口数の合計です。
投資信託の場合、買いが増えれば純資産総額だけでなく総口数も増えます。
なので、買いが増えても基準価額が上がりません。
分かりやすくするため、純資産総額100万円、総口数50万口の仮の商品で説明します。
この商品の基準価額は100万円÷50万口で2万円です。
新たに100万円分購入したとします。
基準価額は2万円なので、50万口購入できます。
これで純資産総額200万円、総口数100万口になりました。
基準価額を計算してみると、200万円÷100万口で2万円です。
もちろん実際には、投資信託に組み入れている金融商品の割合を運用成績によって変えたり、買いや売りによってや総口数も変わるので、このような単純計算にはなりませんが、純資産総額が倍になったのに基準価額は変わりませんでした。
これは、売りが増えた場合でも同じで、純資産総額とともに総口数も減るため、基準価額は下がりません。
結局、運用成績や分配金などによって基準価額は変動しますが、売り買いの増減によって基準価額は変わらないということです。
ですから、基準価額がただ下がっているという理由だけで商品を購入するのは、株とは違って大きく間違っています。

基準価額が下がるとお得感はあるけど、割安とか割高という判断基準自体がそもそも投資信託にはないってことね。

今後V字回復しそうであれば、もちろんお買い得なので購入した方が良いでしょう。
いずれにしても、基準価額が下がった理由を見極める必要があるということです。
というわけで、他にもいくつか間違った常識はありますが、主なものを取り上げてみました。
アクティブ型商品をおすすめする理由



アクティブ型のほとんどがインデックス型よりも運用成績が悪いうえに手数料が高いから、インデックス型をすすめる人が多いんだよね。
何でアクティブ型をすすめてるの?

その優れた商品を見極めさえすれば、インデックス型の商品で運用するよりも効率が良いということです。

何もすべてのアクティブ型が悪いわけじゃないから、インデックス型よりもはるかに儲かる商品を購入すれば良いと。


優れた商品というのは…。
ほとんどがハズレなのに、どうやって見極めれば良いの?
優良アクティブ型商品を見つける方法
シャープレシオと優秀な運用会社&運用担当者


SBI証券のパワーサーチで商品を絞る時にチェックした項目の一つだよね。

リスクに対してどれくらいのリターンがあるかという、運用効率を数値化したものです。
運用効率の良し悪しを判断するうえで参考になる数値ですけど、パワーサーチで検索する際は、よく分からないけど1.0以上なら平均値以上じゃないかという話でした。





アクティブ型というだけで避けていたら絶対に見つけられない商品だよ。


判断基準はシャープレシオ以外にはなかった?



ただ、上昇率の時にもお話しましたが、基準価額が何年も右肩上がりであれば運用担当者が優れている可能性は高いですし、専門家の意見、アナリストレポートなどを参考にすると良いと思います。

動画セミナーとかもあるからそういうのを見ておくと良いんだな。
なるほど。今度時間がある時に見ておこう。
シャープレシオや運用担当に注目することは分かりました。
でもそれだけで良いアクティブ型の商品は見つかるのかな?
優良アクティブ型投資信託は6つの条件で絞り込む


- 購入時手数料が無料(ノーロード)
- 2回以下の決算回数
- 運用実績が3年以上
- 2社以上の金融機関で購入できる
- 同カテゴリー内の商品との比較
- 運用体制や手法の評価



そのため、ある証券会社は販売手数料無料、別の証券会社は3.24%(税込)のようなこともあります。



販売手数料無料の証券会社があるのなら、やはりそこで購入したいですからね。

最初から毎月分配型の商品を除外しているわけだけど。

長期投資を前提とするのであれば、収益分を再投資するためには決算回数が少ない方が良いということです。

では運用実績3年以上というのは?




投資信託の場合、毎年何%の運用で…という未来の運用については机上の空論だと複利の際に話しました。
これが5年10年と運用している商品ならまだ予想できるのかもしれませんが、新商品は運用すらしていないわけですから、毎年何%の運用というのはまったくアテになりません。


しかし、家電や携帯電話などの新商品であれば、今までにない画期的な機能が付いたり、性能がアップしますが、投資信託にはそれがありません。
だから、データが不足してよく分からない新商品はあまりおすすめできないということです。


あとは同じカテゴリー内の『シャープレシオ』、手数料や税金などのコストも含めてその商品の実際の収益が分かる『トータルリターン』、リスクの大きさを示す『標準偏差』を中心に比較します。



ここ1年だけ見ていると本当に良い商品を見つけられないという…。

短期も1ヶ月とか長期なら3年、5年などとさらに細かく比較すればより正確なデータが得られるとのことです。
そして、最終的には各カテゴリーで上位の中から選抜するだけです。


仕方ありません。
でも我々もすぐに良し悪しが分かるようになるかもしれませんから、一つずつ色々な知識を積み重ねていきましょう。

地道に頑張っていこう。

2社以上の金融機関で購入できるというのは、NISAの口座などで一つの販売会社のみ販売している商品を購入しようとする場合、他の商品を購入する際の制約になってしまうからです。
評価というのは専門家によるものです。
なので、先ほどの動画セミナーもそうですが、目論見書やマンスリーレポートなどを参考にして比較していきましょう。
本では以上6つの条件を満たした中から、篠田さんが厳選したアクティブ型投資信託10本を紹介しています。




私は運用成績の良いアクティブ型なら王国の財政を立て直せると舞い上がって、肝心のリスクの分散をすっかり忘れてしまってました。
バランス良く投資しないといけないのに…反省してます。

今回は本当によく調べてくれたから助かるよ。
おかげで今までまったくの対象外だったアクティブ型を検討するきっかけになったわけだし。


で、その10本の中から候補は見つかった?





それまた凄いな。


手数料が高いアクティブ型ばかり選んで、って言ってたと思うけど、実はちゃんと良いのを選んでくれてたのか。
パワーサーチはどうだったっけ?

なので、シャープレシオが高いアクティブ型でも最初から除外されています。





すると、前回はシャープレシオが最大でも1.80でしたが、今回2.0以上の商品が24本も見つかりました。

それは凄いな。







この2つは右肩上がりなのに、販売ランキングは20位とか50位ですし、トータルリターンも100位前後です。

トータルリターン100位?ダメな商品。
ってなってただろうね。

候補にすら挙がらなかったかもしれません。

王国が投資するアクティブ型の商品はその2つで決まりだな。




それにしても今日は家来がよく調べてきてくれたから、本当に勉強になったしタメになったよ。
180度考えが変わるというのは間違いじゃなかった。

今後も頑張って情報を集めてみます。













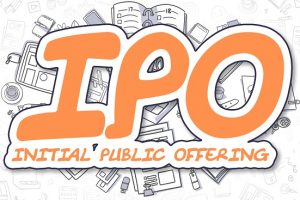





今回で5回目だけど、口座を開設したり、実際に積立投資を始めたりと『財テクキングダムプロジェクト』は着々と進んできました。
さらにこれから投資信託の商品を購入して運用も始めるし、IPOやビットコインなどの新たな投資も始めていくから、プロジェクトを止めることなく前を向いてどんどん進めていこう!